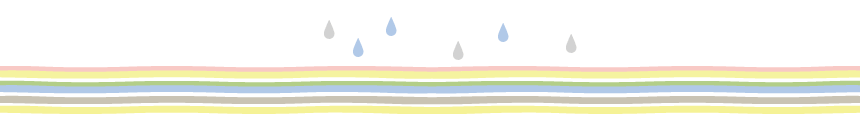Novel迷惑な隣人
教育実習生編
| 実習生が来た! |
|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
| 実習生セルジュ・マツカを加えた4角関係(?) |
お見合い編
| キース先生の事情 |
|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| キース先生に振って湧いたお見合い話 |
完結編
| さよならお隣さん |
|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
| キース先生に振って湧いた異動話 |
さよならお隣さん -11-
ブルーの退院から一週間が経った週末の夜、学校の近くの居酒屋でキースの送別会が開かれた。
「それでは、ブルー先生復帰と・・・ついでにキース先生の栄えある前途を祝って・・・かんぱいー!!!」
「「「乾杯~~!!」」」
小気味良くぶつかり合うグラスの音に、輪の中心にいた人物はしかめ面で音頭をとった同僚を見やった。
「俺はついでか」
「だって、キースの異動なんて大したニュースじゃないけど、ブルー先生は生死の境をさ迷ったんですもの。ねえ、ブルー先生」
スウェナにそう振られて、キースの隣のブルーが困ったように微笑んだ。
「そんな大げさなものじゃないですよ。・・でも、皆さんにはご心配とご迷惑をおかけしました」
「迷惑なんてとんでもない!無事に戻られて何よりですよ」
スウェナは身を乗り出すと、声を潜めてブルーに囁いた。
(記憶も戻ったみたいで、よかったですね)
(ありがとうございます)
(ブルー先生が病院に運ばれた時のキースのうろたえ様・・見せてあげたかったですわ)
「おい、当人を間に挟んで内緒話のつもりか」
「あら?」
ひきつった表情で酒をあおるキースに、彼をからかうスウェナ。
そんな二人のやりとりに、ブルーもまた自然と笑みが零れた。
-----------------------------------------------------
「どこにも行きやしないさ」
優しい包容に、力強い言葉に、それまで心に抑えていた想いが粒となってブルーの頬を、キースの肩口を濡らした。
ただキースの異動を知って、それが思いのほかショックだった。
環境が変われば、関係まで変わるのではないかと思った。
距離が離れれば、心まで離れていってしまうのではないかと疑った。
キースがどこか遠くに行ってしまうような気がして、でも彼を信じられない自分も嫌で・・・
そんなことをぐるぐると考えているうちに、考えることそのものが嫌になった。
「・・ごめん」
「・・?何故お前が謝る?」
「だって僕・・君に迷惑ばっかり・・」
「今に始まったことじゃない」
優しく涙を拭う手が、そっとブルーの頬を包んだ。
出会った頃からずっと、この手に支えられてきた。一途なまでに、自分を想ってくれる彼に。
ブルーは温かなその手に、自分のそれをぎゅっと重ねた。
寂しがることも、不安になる必要も・・何一つなかった。
例え環境が違っても、傍にいなくても、確かな絆はずっとここにある。
-----------------------------------
「おい、なに人の顔見て笑ってる?」
「別に」
なんでもないと微笑むブルーに、キースは仏頂面でジョッキを取り上げた。
「あ」
「そこまでだ」
「いつから君は僕の保護者になったんだい?」
「保護者ならいいがな、潰れた後の介護だけはまっぴらごめんだ。お前には前科があるからな」
「しつこい男は嫌われるよ、キース」
「そうよ、キース。ブルー先生に嫌われちゃってもいいの?」
横からしゃしゃり出てきたのは、ワインボトルを片手にすっかり酔いの回ったスウェナだった。
「・・スウェナ、お前もその辺にしておけ」
「わかってるわよ。それより、次の学校ではもうちょっと愛想よくするのよ」
「余計なお世話だ」
「・・でも、貴方とは実習生の頃から一緒だったから、なんだか寂しいわね。向こうに行っても頑張って」
そう言って右手を差し出してきた彼女に、キースは「ああ」と返すと、彼女の手を握り返した。
何だかんだと言いながらも、良き理解者であり友人だった彼女。
「ありがとう、スウェ・・」
感謝の意を述べようとしたその瞬間、スウェナは握手したキースの手を高々と頭上にかざした。
「はい、二次会行く人この指とまれーー!」
「!?」
「二次会の場所はキース先生のマンションよー!」
彼女同様にできあがった他の教師陣から歓声があがると同時、キースからもまた「ふざけるな!!」という大きな声があがったのだった。
-----------------------------------------------------
「僕もキースの部屋の二次会、行きたかったな」
「いい迷惑だ。・・あの女」
覚えてろよ、と低く愚痴を溢すキース。
宴を終え、二人はいつもの帰路についていた。
今頃、キースの送別会でもブルーの復帰会でも何でもない二次会が場所を変えて、スウェナ主導で行われているだろう。
「あのさ、僕思うんだけど」
「何だ」
「スウェナ先生ってさ、案外キースのこと好きだったんじゃないかな」
「は?」
「恋人の勘」
「・・くだらん」
「くだらなくないよ。キースはもてるんだから、向こうの学校行っても気をつけないと」
「俺よりお前の方が問題だと思うんだがな」
「?」
「例の実習生といい、そういう点では俺はお前を信用していない」
「スタージョン君のこと?あ、そういえばね、キース」
ごそごそと鞄の中から何かを取り出したブルー。
彼が差し出してきたそれは、来年度から着任する予定の教師たちの名簿だった。その中に見知った名前を見つけて、キースは苦虫を噛み潰したような表情に変わった。
「来月から来る新任の先生の中に彼がいるんだよ。すごいよね!あの子、ちゃんと先生になれたんだよ!しかも同じ職場で働けるなんて、嬉しいなぁ」
「・・・せいぜい仲良くしてろ」
「あれ?妬いてるの?」
「別に」
「心配しなくても、僕にはキースだけだから」
ブルーはキースの腕に自分のそれを絡めると、甘えるように寄りかかった。
「離れろ。歩きにくい」
「嫌だ」
そう言いながらも振り払うことはしないキースに、ブルーは満足げに笑みを浮かべたのだった。