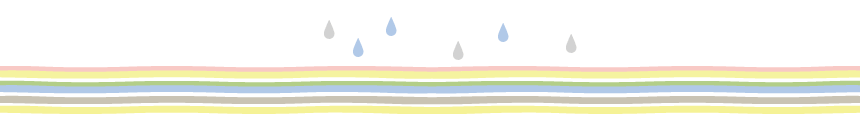Novel迷惑な隣人
教育実習生編
| 実習生が来た! |
|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
| 実習生セルジュ・マツカを加えた4角関係(?) |
お見合い編
| キース先生の事情 |
|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| キース先生に振って湧いたお見合い話 |
完結編
| さよならお隣さん |
|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
| キース先生に振って湧いた異動話 |
実習生が来た! -14-
頭痛い・・・
喉渇いた・・・。
ブルーは重たい目蓋をゆっくりと開くと、ぼんやりとあたりを見回した。
てっきり自分の部屋に帰ったのだと思っていたが、そこは何故かキースの部屋の寝室だった。
(えーっと・・セルジュとご飯を食べて・・・・・・・駄目だ・・全然思い出せない・・)
「やっとお目覚めか」
「・・・?」
すぐ隣を見上げれば、部屋の主が憮然とした表情でこちらを見ていた。
まだ短い付き合いだが、相当ご機嫌斜めらしいということはすぐにわかった。
「・・何でキース?」
「俺がいちゃ悪かったのか?」
「・・そういう意味じゃないけど」
ほら。やっぱり機嫌が悪い。
どのような経緯で自分がこの部屋にいるのかわからなかったが、やけに突っかかる言い方をするキースに、ブルーもまた不快感を覚えた。
「・・お邪魔しました」
なんとなく長居しない方がいい気がして、ブルーはそそくさと部屋を出て行こうとした・・が。
「・・!?」
ベッドから起き上がろうとした瞬間、キースの強い力に抑え込まれた。
「いたっ・・!」
「・・お前・・・」
「な・・なんだよ・・」
「・・俺がこの部屋に入った時、どういう状況だったか覚えてるか?」
「・・・さあ」
とぼけているわけでもなく、本当に何も覚えていないのでブルーはこう答えるしかない。だが、キースの怒りのメーターは完全に振り切ってしまったようだった。
「隙がありすぎるんだお前は!」
「そ・・そんなに怒ることないじゃないか!」
「記憶を無くすほど飲む奴があるか!!それに何だ、あの実習生は・・!」
セルジュのことを指しているのだろう。まだ記憶はあいまいだが、やはり彼がここまで自分を送ってくれたことは間違いないようだ。鞄の中にはキースの部屋の合鍵が入っていたため、それを間違えて使用してここに運んでくれたのだろう。
何にしても、ひったくりの件といい今日は本当に彼には助けられてばかりだな・・とセルジュへの感謝を改めて感じたブルー。
そんな恩人・・否、可愛い後輩を指して何だとはなんだ。
ブルーもまた、キースに怒りを覚えた。
「何って・・僕を送ってくれたんだよ、セルジュは」
「ほう・・?名前で呼んでいるのか。随分と仲のいいことだな」
「ああそうだよ。今日一日で随分と仲良くなれたんだ。話してみるとすごく紳士的でいい子だったよ・・・君みたいな浮気者と違ってね」
棘のある会話の応酬の最中、ブルーの言葉にキースが眉をひそめた。
「?・・なんのことだ・・??」
この後に及んでシラを切るつもりなのか・・・・なんて男だ!
「自分の胸に手を当ててよーく考えてみれば!」
「??」
まだわけがわからないといった顔をするキースに、ブルーは怒りを通り越して悲しくなってしまった。
「僕のこと・・飽きたなら飽きたって・・言えばいいじゃないか・・僕に黙ってあんな・・」
そこから先を言おうとするも、不意に涙が眼に浮かぶ。
大粒のそれをぽとぽとと溢し始めたブルーに、キースは当惑しながらも先程より口調を和らげて再び問いかけた。
「?・・さっきから何を指して言っているんだ?・・全く話がつかめないんだが・・」
「今日の放課後・・マツカと・・き・・キス・・してたじゃないか」
「は?俺がか・・?」
「ちゃんと・・この目で見たんだよ」
正確にはキスシーンそのものではないが、誰が見てもあの状況はこれからそういう行為に及ぶとしか思えないものだった。
「・・・」
しばし何かを考えていたキースだったが、ああと思い出したように一人納得した。
「どうも最近様子がおかしいと思ったら、お前・・・マツカに焼いてたのか」
感心したように、そしてどこか嬉しそうにキースが言った。
図星だというのに、ブルーは真っ赤になって全否定した。
「!・・違う・・断じて違う・・!」
「なるほどな・・だが、その腹いせに人の部屋に男を連れ込むとは関心せんな」
「ちがっ・・・」
満足げに微笑むキースの顔が近付く。
自分だけ全て把握したような顔をして・・気に入らない。
だが、まっすぐに自分を見つめるキースの瞳から眼が離せず、ブルーは抵抗することなく、彼の唇を受け入れた。
「・・あいつとは、お前の想像しているようなことは何もなかった」
「・・ほんと・・に?」
「ああ。マツカはただの後輩だ。それ以上でもそれ以下でもない」
「・・・」
「・・信じられないか?」
涙を拭うキースの手。
信じられない・・はずはなかった。
自分がどうしようもない時・・支えてくれた、キースの深い優しさ。
本当は、その手が自分を裏切ることなどないと、ブルーもまた心の底ではわかっていた。
ただ、少しだけ以前と過ごし方が違って・・・見たことのないキースを見つけて不安になって・・。
だから、試したかったのかもしれない。
「・・・疑って・・ごめん」
「・・構わんさ」
「ちょっと・・妬いてたみたい」
「ちょっと・・か?」
二人は顔を見合わせて微笑むと、今度は溶けるように甘い口づけを交わした。