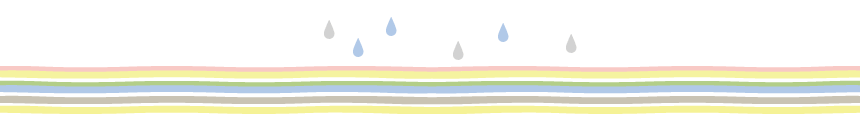Novel迷惑な隣人
教育実習生編
| 実習生が来た! |
|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
| 実習生セルジュ・マツカを加えた4角関係(?) |
お見合い編
| キース先生の事情 |
|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| キース先生に振って湧いたお見合い話 |
完結編
| さよならお隣さん |
|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
| キース先生に振って湧いた異動話 |
さよならお隣さん -5-
「何の・・・冗談だ・・?」
困惑した表情のブルーに、キースもまた戸惑いを覚えた。
まるで知らない人だと向けられた視線は、怯えたような気配すら感じさせた。
「手・・・」
「・・・?」
「・・離して下さい」
キースは不可解な現象に為すすべもなく、言われるままに、握りしめていた彼の手を離した。
「お待たせ~。ねえ、本当にこれでよかったの?キース・・・・?!ブルー先生・・!」
缶コーヒーを抱えたスウェナは室内に戻るや否や、ブルーの目覚めに歓喜した。
「よかった!気が付かれたんですね」
「・・スウェナ・・先生・・?僕・・一体どうしたんですか・・?ここは・・・?」
「あら?何も覚えてらっしゃらないんですか?学校の階段から落ちて、この病院に運び込まれたんですよ」
「そうだったんですか・・すいません、ご心配をおかけして・・」
「いいんですよ。ブルー先生がご無事なら。それに心配というのなら、私よりもそこの人の方が何倍も先生のこと心配していたんですよ」
そこの人、と指を指して先程までのキースを笑うスウェナ。
だがブルーといえば、彼女に接するそれとはまったく違う様子でキースに視線を移した。
「あの・・・スウェナ先生、この方はスウェナ先生のお知り合いですか?」
「え・・?」
ここにきてようやく、ブルーの身に起こった異変にスウェナも気付いた。
「な・・何仰るんですか?・・キース先生じゃないですか」
「・・?キース・・先生・・?」
悪ふざけでも、演技でもなく、本当に知らないという顔をしたブルー。
キースとスウェナは、互いに困惑した表情で顔を見合わせた。
----------------------------------------------------------------
「脳震盪を起こした患者さんが、事故前後の一時的な記憶を忘れることは珍しくありません。ですが、一人の人間の記憶だけを忘れるなど・・・私も聞いたことがありません」
「そう・・ですか」
医師の言葉に落胆するスウェナ。
彼女の視線を受けて、それまで黙って聞いていたキースが医師に問いかけた。
「記憶が戻る可能性は?」
「外傷による記憶障害であれば、徐々に回復していく可能性は高いですが・・」
医師はあくまで専門外ですが・・と言いながら続けた。
「人は重度の心的外傷を受けた際にも、健忘を起こす場合があります。あるいは今回の事故とは直接関わりなく、何らかの心因性のストレスが原因となって、特殊な形で記憶障害が現れている可能性も捨てきれません」
検査の結果次第では、そちらの方面の医師の治療も必要になるかもしれない。
だが、現時点ではあくまでブルーの記憶障害の原因はわからないと医師は念を押していた。
「またお葬式みたいな顔して。すぐに思い出してくれるわよ」
「・・・だと、いいがな」
ブルーの病室へと戻る途中、キースは先程の医師の言葉を見つめ直していた。
ブルーは、キースのことだけを忘れてしまっていた。
階段から落ちた際の記憶は曖昧ではあったが、自分が教師であることは勿論、同僚であるスウェナのことなど、他の全てのことについての記憶はしっかりと持っていた。
キースの存在だけが、ブルーの世界からいなくなっていた。
そんなおかしな記憶喪失など、聞いたことがない。
医者の言う通り、今日の事故だけが原因だとは確かに思えなかった。
『心的外傷』『心因性のストレス』
医師の口から出た言葉が、キースに重くのしかかっていた。
自分は彼に何かしただろうか。
自分を忘れてしまうくらい、忘れたいと思うくらいに傷付けるような事をしただろうか。
いくら考えようとも、乱れた思考では答えは出なかった。
「じゃあブルー先生、私たち、今日はこれで失礼しますね」
「ありがとうございます、スウェナ先生・・・それに・・・」
「・・・」
「キース、先生・・でしたよね」
「・・ええ」
先程のような警戒の色は失せたが、ブルーはまるで初対面の人間の名を確認するような態度だった。キースはただ彼に調子を合わせるしかなく、そんな自分が少しおかしかった。
「・・ブルー・・先生、よろしければそれ、お飲みになって下さい」
「?」
キースはサイドボードに置かれたコーヒーの缶を指差した。
医師の元へ事情を説明しに走ったため、結局手をつけられずじまいだったミルクコーヒーだ。
「・・よろしいんですか?」
「・・はい」
「僕・・甘いの好きなんです。ありがとうございます」
まるで知らない人間だ。
お前にとって俺は、その程度か?
他人事めいたブルーの笑顔に、キースの中でふいに何かが切れた。
「・・馬鹿馬鹿しい・・演技もそれぐらいにしたらどうだ?」
「え?」
「本当に忘れたのか?俺だけを?」
「キース・・先生・・?」
「そんな都合のいい記憶喪失があってたまるか」
つかつかとブルーの元へ歩いていくと、キースは乱暴に彼の襟首をつかんだ。
「っ・・!」
「ちょっと、キース!」
「思い出せ!さあ、今すぐ思い出してみろ!・・それとも、下手な演技をやめるか?」
「・・っ・・僕には・・・何の・・ことだか・・」
苦痛に歪むブルーの表情から、恐怖の感情が露わになる。
「しらばっくれるなッ!!」
「キースやめてあげて!!」
スウェナの強い制止に我に返ると、キースはブルーの寝間着の襟を解放した。
小さくなり、怯えたブルーが恨めしげにこちらを見ていた。
「どうして・・そんな・・・乱暴なことするんですか?」
「僕はあなたのことなんて・・知らない」
どうしてこうなったのか。
キースは彼から顔を背けると、声をかけようとしたスウェナさえも無視して病室から出て行った。