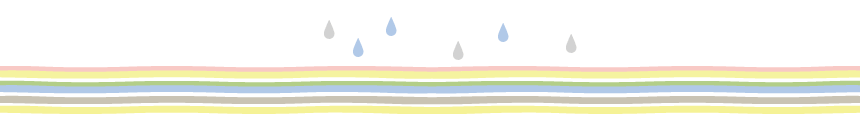Novel迷惑な隣人
教育実習生編
| 実習生が来た! |
|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
| 実習生セルジュ・マツカを加えた4角関係(?) |
お見合い編
| キース先生の事情 |
|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| キース先生に振って湧いたお見合い話 |
完結編
| さよならお隣さん |
|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
| キース先生に振って湧いた異動話 |
さよならお隣さん -7-
「・・ということで、着任前に一度顔を出しておいて下さい。日程についてはあちらの教頭先生と調整をして・・・・・キース先生・・?」
「・・あ・・はい、わかりました・・・」
心ここにあらずといった様子で返事をすると、キースは右から左に流しかけた教頭の話を慌てて頭に詰め込んだ。来月の人事異動が、もう目の前に迫っていた。
こんな状態で、行けるのだろうか。
教頭室から出たキースは、異動先の資料を見つめて深い溜息を落とした。
ブルーの入院からもうすく一週間が経つ。だが、彼が自分を思い出す気配は全くない。
それどころか・・・。
キースはブルーの入院初日の自分の行動を悔いてやまなかった。
あれでは完全に嫌われた。
向こうが初対面と言い張るなら、さぞ最悪の第一印象を与えたことだろう。
キースは何もかも終わったような心境だった。
終わり・・?
自分たちはこれで終わりなのだろうか。
こんなことで終わってしまうのだろうか。
終わらせてたまるものか、と自分のマイナスに走りかける思考を奮い立たせるキース。
だが、これといった解決策も浮かびはしない上に、彼の記憶喪失の原因が自分ではないかと思うと、それはそれで気が滅入るのだ。
どうしたらいいのだろう。
どうしたら思い出してくれる?
自分一人ではとても抱えきれない状態までキースは追い詰められていた。
かといって、誰かに相談したくともそんな立ち入った話ができる相手など・・・
「キース先生」
「・・・?」
職員室の前を通りかかると、背後からの聞き覚えのある声に呼びとめられた。
振り返ると、卒業を控えた3年の教え子が傍に立っていた。
「ジョミー・・か。・・何だ?」
「あの・・ブルー先生、入院されたって聞いたんですけど・・具合はどうなんですか?」
「ああ・・・大した怪我じゃない」
「そうですか・・よかった」
それまで心配を顔に浮かべていた少年が、ほっと胸をなで下した。
心底ブルーの容体が気がかりだったのだろう。
彼とは授業中に言葉(主に課題忘れに関して一方的に叱咤するだけだが)は度々交わしていたが、こうしてブルーについて直接話をするのは初めてだった。
以前の担任教師・・・元恋人。
確かに気になって当然か。
ジョミーが今でもブルーを想っているのか、あるいは純粋に師弟の感情で彼を想っているのかは未だにキースの知るところではないが・・今となっては、少年との浅からぬ因縁に懐かしささえ覚えたのだった。
「?・・キース先生ちょっと痩せました?・・痩せたっていうか、やつれ?」
「・・・そう見えるか」
「なんかいつも以上に暗いっていうか・・・ブルー先生、ほんっとーに大丈夫なんですか?」
意外にするどいところを突いてくる少年に、キースはある考えに至った。
前言撤回。立ち入った話だが、話せる相手は確かにいる。
これを彼に言ったとして、何がどうなるわけでもない。だが、何がどうなる前に、今彼に吐露しないことにはキース自身がどうにかなってしまいそうだった。
「ジョミー、放課後・・視聴覚室に来い。話がある」
「え・・?」
--------------------------------------------------------
そしてその日の放課後。
防音効果のある黒いカーテンに隔てられた視聴覚室の中で、キースはブルーの現在の状態をジョミーに話した。
「記憶喪失ぅぅう!!!?」
「馬鹿、声が大きい!」
防音と言っても布一枚隔てた廊下では、数人の生徒が清掃を行っている最中だった。
だいいちブルーの記憶の件は、スウェナを除いて公にはしていない。
「すいません・・」
キースのげんこつを食らって、ジョミーは何も殴らなくても・と付け加えながら頭を撫でた。
「記憶喪失といっても安心しろ。恐らく、お前のことは覚えている。あいつの頭の中から消えたのは俺だけだ」
キースの言葉に、ジョミーは大きな瞳をぱちくりとさせた。
「・・・何でまたそんな・・ややこしいことに?」
「さあな・・それがわかれば苦労はしない」
「どうせ、キース先生が傷つけるようなこと言ったんじゃないですか?」
ジョミーは冗談のつもりだったが、キースはその一言に酷く暗い表情を浮かべた。
「・・そうかもしれんな」
「あ・・・いえ、あの・・そんなに本気で落ち込まれても・・・」
漂う気まずい雰囲気にぽりぽりと頬をかいていたジョミーが、思い出したように切りだした。
「そうだ、キース先生・・来月から別の学校に行くんですよね?」
「・・?ああ、そうだが」
「案外それが原因なんじゃないですか?」
「何故・・?」
「だって、今まで何年も一緒に働いてた恋人が急に別の土地に行っちゃうってなったら、相当ショックだと思うんですけど」
「しかし・・そんなことで記憶を無くしたりするものか?だいいち・・あいつはあの時・・・」
異動が決まったと話した時、ブルーは笑っていた。
笑顔で送り出そうとしてくれていた。
寂しいという一言すらなく、弱音など一切吐かずに・・。
「これは例えば・・ですけど。キース先生の異動が嫌で、キース先生の異動のこと考えるのが嫌で・・キース先生のこと考えるのが嫌で・・・って感じで、頭打ったショックもあって全部綺麗に忘れちゃった・・とか」
「・・・」
「あの人だったら、そういう突拍子もないこと・・ありそうじゃないですか?」
「・・・確かに」
あの時、笑顔の裏でブルーがどんな思いでいたのか・・自分はすっかり見落としていた。
送られた笑顔をそのまま受け取って、それに少しばかり物足りなさを感じて・・・・愚かだった。
この目の前の少年は、そんなブルーの内心を余程自分よりも把握しているのだ。
そう思うと、風化していたはずの嫉妬心が僅かにキースを刺激した。
「ありがとう。参考になった。・・あとはこっちでなんとかする」
「こっちでって・・・そんなに張り合わなくたって、僕もう別にキース先生のライバルでも何でもないですし」
「・・・」
別に張り合ってなどいないつもりだが。
『恋人の昔の男』を意識しているように思われているのが、キースとしては心外だった。
「それより、僕もお見舞い行っていいですか?ブルー先生の」
「明日退院だぞ」
「じゃあ、今から」
「・・・行きたければ行けばいい。何故俺に了解を取る?」
「・・いや、だって一応・・・元恋人だし・・」
「意識する必要はない」
「意識してるのそっちじゃないですか」
やはり彼には・・・彼にだけは相談すべきではなかったかもしれない。
そう思ったキースだった。