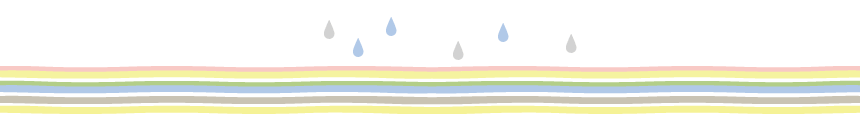Novel迷惑な隣人
教育実習生編
| 実習生が来た! |
|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
| 実習生セルジュ・マツカを加えた4角関係(?) |
お見合い編
| キース先生の事情 |
|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| キース先生に振って湧いたお見合い話 |
完結編
| さよならお隣さん |
|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
| キース先生に振って湧いた異動話 |
さよならお隣さん -6-
頭の中で声がする。
嫌だ、嫌だ、としきりに訴えている。
思い出したくない。
思い出したら失ってしまう。
遠くへ行ってしまう。
ブルーは大事をとり、1週間の入院生活を送ることとなった。
意識喪失の時間が比較的長かったため、念のための休養と、脳の細部を改めて検査する必要があると医師が判断したためだ。
事故から三日が経ち、個室から相部屋に移ったブルーは一通りの検査を終えていた。
手持無沙汰な入院生活だったが、親しい教師や教え子の訪問のお陰で、幾分気は紛れつつあった。
そして今日は、事故のきっかけである女子生徒たちが、見舞いに訪れていた。
「ブルー先生・・ごめんなさい」
「謝る必要なんてないよ。君たちに怪我がなくて本当によかった」
「でも・・」
「ほら、この通り僕は元気だから。君たちも笑って。来週からは学校で元気な顔見せてよ」
終始申し訳なさそうな彼女たちの沈んだ表情を和らげようと、ブルーは両手の拳を握って彼に似合わぬ仕草で無事を強調した。
彼女たちと接するうち・・正確にはこうしてベッドの上で落ち着いて物を考えるうちに、ブルーはどういう経緯で自分がここにいるのかをすっかり思い出していた。
生徒を助けるために階段から落ちたのだ。
全く、我ながら間抜けだなとブルーは思った。
「じゃあ、ブルー先生お大事に」
「うん、ありがとう」
生徒たちに笑顔で手を振ると、彼女たちと入れ替わるように一人の教師が入ってきた。現れた漆黒の髪の男に、ブルーの笑顔が張り付いた。
「あ・・」
「・・」
「何の・・用ですか」
同僚教師のキース=アニアン。
先日からずっとそう聞かされているが、彼のことなどブルーは知らない。
初対面と言い張るブルーに彼は不快感を持っているようだが、ブルーだって、さも見知った仲のように振る舞う彼が不快だった。
それに先日の暴力行為。ブルーは彼に対して当分拭えそうにない、最悪の印象を持ってしまった。
「ご挨拶だな。お前の着替えの替えだ」
「・・?何であなたが?」
僕の着替えまで世話するんだろう。そう疑問に思ったところで返事があった。
「隣だからだ」
「職員室の席が?」
「マンションもだ」
「そうなんですか?」
「そんなことも忘れたのか、お前は」
「お前お前って、僕にはブルーという名前があるんです」
「だったらお前もその他人行儀な話し方をやめろ」
「・・・他人じゃないですか」
そう言葉を発した瞬間、キースが僅かに寂しげな表情を浮かべたような気がした。
どうしてそんな顔、するんだろう。
まるで僕が悪い事言ったみたいじゃないか。
「・・他に必要なものがあればスウェナにでも言え。俺の顔を見るのが嫌なら、今後はあいつに預ける」
「・・別に嫌とは」
「嫌だから、忘れているんだろう・・」
そう吐き捨てると、キースは病室を出て行ってしまった。
残されたブルーは渡された着替えの袋を見つめた。
「そういうわけじゃ・・ないけど」
「・・??」
自分が何を言ったのかわからず、ブルーははたとした。
本当は・・・わかってる。
今の自分は何かが決定的に欠けている気はするのだ。
でも・・仮に、彼について失った記憶があるとして、彼には申し訳ないけれど、今の自分がそれを覚えていないことに支障を感じていないことも事実なのだ。
職場の同僚、聞けば職員室の席もマンションも隣人だという。
そんなに親しい間柄だったのだろうか。あの野蛮な教師と?
横道に反れそうな思考を軌道修正して、ブルーは肯定的に考えた。
確かに、親しい友人が自分のことだけをすっかり忘れてしまったとなれば、彼の憤りもわかる。でも、だからといって、記憶を取り戻す術をブルーは知らない。
そもそも彼についてどんな記憶を持っていたかすら思い出せないのだ。
ひょっとしたら、さほど大した記憶ではないのかもしれない。
そこまで考えて、ブルーは首を振った。
・・大した記憶じゃなければ、あんな風に悲しそうな目はしない。
なんとなく、彼が悲しむ姿は見たくないと思った。
でもその思いとは裏腹に、彼のことを考えると恐怖で心の奥がざわざわと波打った。
思い出さない方がいい。
それは怖くて寂しいもの。
何かがそう訴えていた。