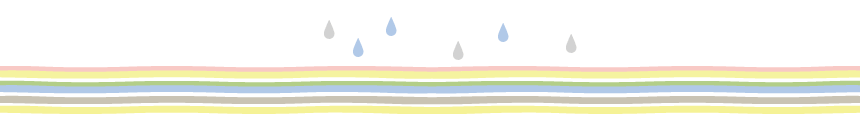Novel迷惑な隣人
教育実習生編
| 実習生が来た! |
|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
| 実習生セルジュ・マツカを加えた4角関係(?) |
お見合い編
| キース先生の事情 |
|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| キース先生に振って湧いたお見合い話 |
完結編
| さよならお隣さん |
|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
| キース先生に振って湧いた異動話 |
さよならお隣さん -4-
放課後を待たずして、キースはスウェナとともにブルーの搬送先の病院へと向かった。
その途中、彼女の指示でブルーの寝間着や着替えをマンションに取りに行った。
「2~3日分でいいわ。あとは多めのタオルと歯ブラシと・・・そうそう、スリッパもね。案外困るのよ、病院の中の履物」
キースはただ、彼女の言う通りの品をブルーの部屋から持ってくることしかできなかった。
運転席の彼女の横顔が、普段のそれより凛としたものに感じる。
こういう非常時などは特に感じるが、女とは強い生き物だなとつくづく思った。
それに比べて自分は・・・。
キースは今まで、自分を強い人間だと思ったことはなかった。
かといって、弱い人間だと思ったこともなかった。
だが今の自分は何だ?
スウェナに引っ張られ、なんとかこうしてここにいる。
奮い立たされ、やっとの思いで息をしているような感覚だ。
そんな自分が信じられなかった。
(ああ、そうか)
(あいつが・・・あいつだからか・・・)
ブルーがいかに自分にとって大きなウェイトを占めた存在か、キースは改めて感じたのだった。
「もう、お葬式に行くみたいな顔して!大丈夫よ。あんなに素敵なブルー先生を、神様が助けないはずないわ」
「・・・ああ」
普段なら嘲笑するはずのスウェナの楽天的な励ましが、今のキースには心地良かった。
病院に到着した二人は、受付で得た情報からブルーの眠っているという個室へ向かった。
病室に入ると、付き添いで救急車に乗り込んだ保健医のノルディがベッドの脇にかけていた。
「ああ、キース先生にスウェナ先生」
「付き添いありがとうございました、ノルディ先生」
頭を下げたスウェナに続き、キースも会釈をする。
保健室に世話になる機会など皆無だったため、キースがこの保健医と間近で接するのはこれが初めてだった。
「お二人とも、授業はよろしいのですか?」
「私たち空き時間なんです。終礼は生徒に任せてきていますし。それより、ブルー先生・・・いかがですか?」
ベッドの上のブルーに皆の視線が集まる。
昼に言葉を交わしたばかりの彼は、その時のままの衣服で寝台に横たわっていた。
「頭を強く打ったようでしたが、検査の結果では脳に異常はないそうです。医師は脳震盪だろう、と」
「そうですか」(よかったわね)
後ろで沈黙していたキースを、スウェナがつっついてきた。
キースは二人のやりとりに口を挟むこともなく、ただブルーの寝顔を見つめていた。
まるで御伽話のお姫様だった。
あまりに穏やかな寝姿に、このまま目を覚ましてくれないのではないか・・・などという錯覚さえ覚えはじめてキースは頭を振った。
「私は学校に報告がありますので、あとはお任せしてもよろしいですか?」
「ええ、構いませんわ」
ノルディが病室を出て行くと、スウェナは彼が座っていた椅子にかけるように促してきた。
「王子様のキスで目が覚めるかも知れないわよ」
「・・・馬鹿言うな」
なんだか自分の思考が見透かされたようで、キースは少し恥ずかしかった。
「私、飲み物買ってくるわ。コーヒーでいい?」
「ああ。・・・ミルクと・・砂糖入りを頼む」
「へ・・・?あなた、ブラックが好きなんじゃなかったの?」
『何って?コーヒーだよ。キースの好みがわからないからさ、とりあえずミルクと砂糖入れてみた』
『入れた方が美味しいよ』
「たまには飲みたい時もあるさ」
思い出に浸るあたり、相当自分は限界だなとキースは二人きりになった病室で苦笑した。
「ブルー・・・目が覚めたら、一緒に暮らそう」
何も返してくれない寝顔を見つめながら、昼間言えなかった台詞を呟いた。
彼の細い指に触れたその時だった。
「ん・・・」
「?!」
僅かな目蓋の動きに合わせて、彼の長い睫毛が揺れた。
「ブルー・・?」
ゆっくりと開かれたそれから、二つの赤い宝石がキースをぼんやりと見つめていた。
「・・・」
「ブルー・・」
キースは彼の手を両手で握りしめていた。
今までの不安が一気に溢れて、すぐにでも彼を抱き寄せてしまいたかった。
「・・まったくお前はっ・・心配ばかりかけて・・・」
なんとか悪態を絞り出す。
情けない話だが、溢れようとする嗚咽を抑えるのに必死だった。
「・・・あの、」
「?」
「誰かと・・間違えてません?」
「・・・」
起きぬけのジョークにしては質が悪い。
信じがたい表情でキースはブルーを見た。
「僕・・あなたのこと知らないんだけど」
ブルーは冗談を言っているようには見えなかった。